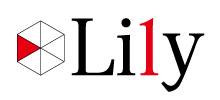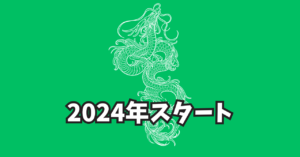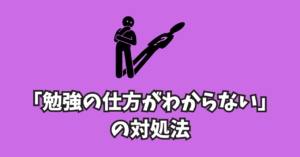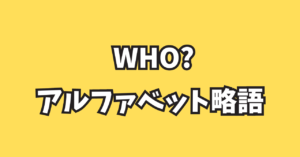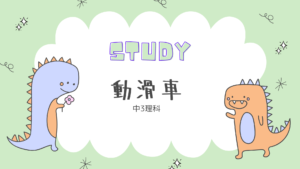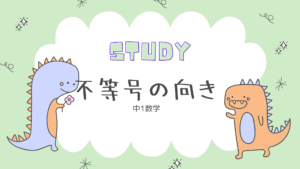中学2年生の茨統に対応するため、幕末から明治時代を集団授業で扱いました。
江戸時代だけでも260年、武士の政権が始まった鎌倉時代から考えると700年。
長い間、武士が中心の世の中でしたが、それが変わるという歴史の大転換点。
それが幕末から明治。
そこから欧米列強に肩を並べるまで成長する、日本の飛躍の時代です。
なかなかおもしろい時代ですが、人物も用語も多くなって勉強するには大変な時代。
なんとか簡単に、わかりやすく説明しようとする僕です。
明治時代が明けてすぐに、スーパースターを集めた岩倉使節団が形成され不平等条約改正の交渉のため海外へ派遣されました。
実際にはまだまだ条約改正の交渉などできず、結果的には海外視察で終わってしまった使節団ですが、得るものは大きかったようです。
一方、留守を任された板垣退助と西郷隆盛。
富国強兵と殖産興業をスローガンに、新しい日本を固めていきます。
そんな日本にも、いろいろと不満をもった人たちがいて、とりわけ士族の不満は大きいものでした。
もともとは武士である士族は、激しい時代の流れの中で必要とされなくなってきていたので、その不満が大きいのも頷けます。
そんな不満を和らげようと、留守政府は征韓論を唱えます。
アメリカが日本をそうしたように、武力をもって朝鮮を開国させようという主張です。
征韓論は、帰ってきた岩倉使節団によって「そんなことより国内の体制樹立が優先だ!」と一蹴されてしまいました。
留守を預かっていた板垣退助と西郷隆盛はやがて政府を去ります。
そして板垣退助は自由民権運動を始め、西郷隆盛は最後の武士の反乱である西南戦争を起こし散っていきます。
こんな明治時代初期ですが、日本を一つの家として見ると身近に感じられるんじゃないかと思います。
岩倉使節団=父親
留守政府=母親
士族ら=子供たち
といった具合です。
まず父親(岩倉使節団)は、仕事で出張に行きます。
2年もの長い期間ですが、仕事ですから仕方ありません。
母親(留守政府)は、父親がいない中でも奮闘して、家のルールをどんどん決めていきます。
しかし、子供たち(士族ら)が騒ぎ出します。
「ずっと家にいるの、つまんない!外に行きたい!」
母親はそれをなだめますが、それも限界に近づいてしまいます。
ちょうどそのとき、父親が帰ってきました。
母親「おかえりなさい。あのね、今、家では外に行こうって話で持ちきりなの」
父親「そんなことより、家の体制をしっかり決めるぞ」
母親「そんなことよりって……こっちはあなたがいない間も、子供たちをうまくなだめながらずっと頑張ってきたんですよ」
父親「外を見てきた俺にはわかる。我が家はまず、家の中のことをしっかりやるべきだ」
母親「じゃあ、外へ行くっていう話は……」
父親「そんなもん、当然なしだ」
母親「……どうやら話し合っても無駄なようですね。出て行かせてもらいます……」
こんな感じの一家のドラマ。
その後母親は「もっと家族の話を聞け!」と主張したり「このわからず屋がぁぁ」と言って反乱を起こしたりしました。
 友人Y
友人Y母親、ファンキーだな
こんなふうにすると、明治時代の日本のリーダー達のやりとりも身近に感じるかなぁと思って、Lilyではこうやって説明してます。
歴史は戦国時代だけでなく、その他の時代も面白いし、現代を生きる上でも役に立つので一石二鳥の学問だと思います。
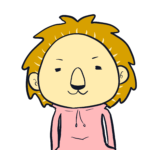
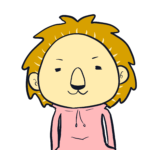
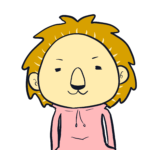
この楽しさ、リリイっ子に伝わってくれるといいなぁ