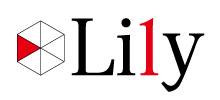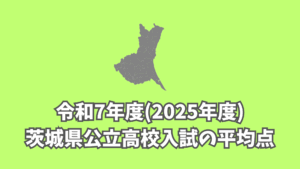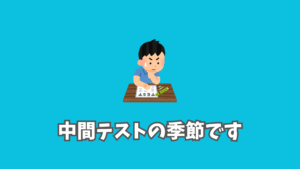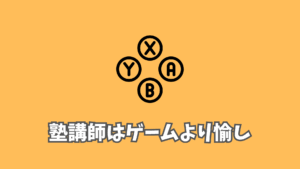新8年生(新中2)の集団授業はなぜか人がいっぱいいます。
他の学年に比べて集団授業の参加率が高いのです。
それに加えて、自立型個別指導で学習している子も多いので、満席になりそうな勢いなのです。
15時30分~16時50分という時間がちょうどいいんでしょうかね。
そんな新8年生は今日の授業では茨統の理科の過去問を扱いました。
1年分解いてみましたが、得点の幅は大きかったです。
数学の統計の分野でいう「範囲」は60点といったところでしょう。
各々の得点は30~90点でした。
その違いは一目瞭然です。
「基本的なことを忘れていれば30点、覚えていれば90点」です。
ちょっとここで深堀してみましょう。
なぜ忘れてしまうのか。
この答えは2つあり、1つは興味がないから、もう1つは反復してないからです。
人間、興味がないことはすぐに忘れます。
脳の容量を節約するために、そうなっているようです。
誰かの誕生日を聞いたところで、その人に興味がなければすぐに忘れてしまうでしょう。
逆に興味があれば忘れません。
そういえば私の娘も、ポケモンの名前の暗記に驚くべき能力を発揮しています。
かくいう私も子どもの頃はドラゴンクエストやファイナルファンタジーのゲームの魔法を覚えていました。
当時の小中学生男子ならみんなそんな感じだと思います。
メラ、メラミ、メラゾーマ。
ホイミ、ベホイミ、ベホマ、ベホマズン。
ギラ、ベギラマ、ベギラゴン。
名前も効果もしっかり頭に入っています。
興味があるものは、反復するなと言われたって勝手に反復しているので、自動的に記憶に残りやすくなります。
融点、沸点、沸騰、蒸発、蒸留……
ポケモンの名前に比べたら、だいぶつまらなそうで難しそうですね。
反復する気も失せてしまいます。
でも、ポケモン並に覚えやすいと思うんですよね。
例えばピカチュウは「ピカっと光ってチュウチュウ鳴く」という雷とネズミをイメージしたものでしょうから、ピカチュウと名付けられているのだと思います。
ヒトカゲとかフシギダネとかニャオハとか、そういった「ネーミングが推測できるキャラ」であれば覚えるのは楽です。
でも「ラプラス」だの「フィオネ」だと言われても、全く推測ができないキャラは覚えられません。
ただ、ポケモンは「ボルケーノ(火山)をモチーフにしてるからボルケニオンって言うんだろうな」という推測できるキャラ、つまりモチーフがわかるキャラが多いので、覚えやすいような気もします。
子どもたちはまだ「火山を英語でボルケーノと言う」ということは知らないでしょうから、覚えるのは楽じゃないと思うですけどね。
大人の方がポケモンを覚えるのが有利な気がしますが、そこはやはり興味の差で、子どもに負けますね。
理科の用語はというと…
「物質が融ける、つまり固体が液体になるところだから融点」
「物質が沸騰するところだから沸点」というように、ほぼすべて推測できると思います。
蒸留だって「液体を一度”蒸”発させて、その後冷やして液体として”留”めるから蒸留」と覚えれば、再結晶との区別もできます。
再結晶は「固体を一度液体に溶かして、その後冷やして再び固体として取りだす(結晶をつくる)から再結晶」です。
これを「一回なんかして、その後冷やして、またなんかする」くらいの曖昧な覚え方でいると蒸留と再結晶の二択に迷うことになります。
用語はわかりやすいとはいえ、興味を持てるかというと、結構微妙な気がします。
そこはやりポケモンのほうが興味を持ちやすいでしょうしね。
ということで、興味を持つのは諦めたとしたら、残るは反復のみ。
反復は「覚えようとする気持ち」があるかどうかで、取り組み方が変わります。
「覚えようとする気持ち」は「テストて点数を取りたい気持ち」と言い換えてもいいでしょう。
こういう気持ちがあるなら反復もできるはず。
逆に「別にテストの点数なんて気にしない」というのであれば、そういう子に反復練習をさせるのは難しく、点数を上げるのも困難になります。
ということで、勉強に向かう気持ちが表れやすい理科。
鬼門ですよ。
頑張りましょう。