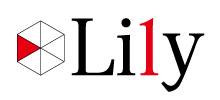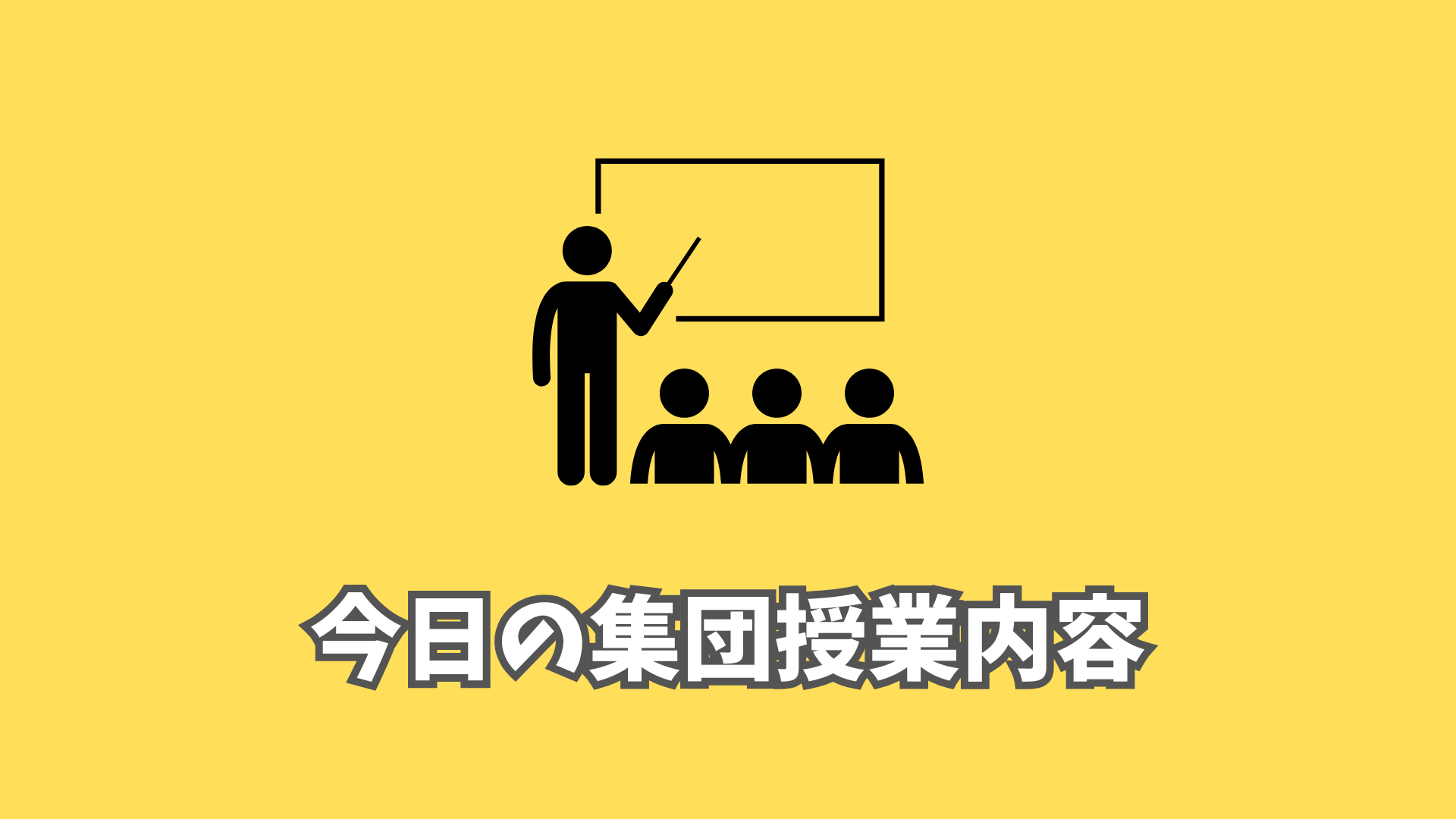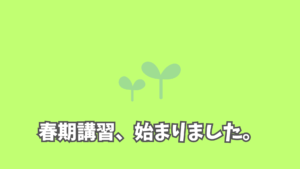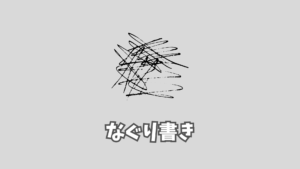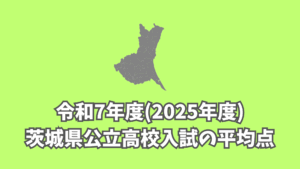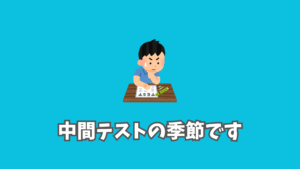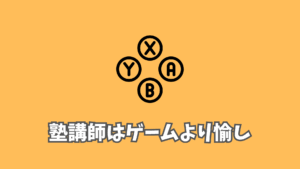普段は一日一コマの集団授業しかやらないので、春期講習のように4コマ連続でやるのは大変です。
大変ですが、楽しいです。
「楽じゃないけど楽しい」って感じです。
今日はどの学年も、先取り授業を行いました。
新7年生は英語。
新7年生は現在1名しかいないので、集団授業といいつつ個別指導みたいになってます。
この子はすでに英検5級も取得しているので、中1英語はお手のもの。
と、思いきや少し抜けがあるので、そういう部分を学習しました。
新8年生も英語。
茨統過去問を見せつつ、これからは動詞は原形だけを覚えるだけじゃ駄目という話をしました。
speak – spoke – spoken のように、原形(現在形)ー過去形ー過去分詞形の3つをテンポよく覚えなければなりません。
過去分詞は8年生の最後に習うので、出てくるのはまだまだ先ですけれど、今のうちから覚えておいて損はありません。
せっかく過去形を覚えるのですから、ついでに過去分詞までやっちゃえってことで。
ただ、授業では扱っても、それはほんの一回だけ。
これだけで覚えられる人はいないでしょう。
この後、自学などで何度も練習するかどうかで、未来がだいぶ変わってきます。
さぁ、リリイっ子新8年生の未来やいかに。
新9年生は数学の展開と因数分解。
どの学年も、数学は計算問題から始まるのですが、9年生の計算問題はちょっと手こずります。
平方根という新しい概念が入ってくるからです。
ということで、たかが計算問題だから皆できるでしょって甘く見ていると、そこでついていけなくなってしまう子が出てきてしまいます。
なので、9年生の計算問題は最初から全力投球です。
問題をモニターに映し、一斉に解き始める。
こうすることで、解くスピードを意識させています。
普段、計算が苦手な子もちゃんとついてこれました。
9年生のスタートダッシュは成功しそうです。
新高校1年生は数学の命題と証明。
「『生徒会長ならば生徒会役員である』この真偽を答えなさい」といった感じの、今までの数学とは一味違った分野です。
数学の知識を使いつつ、国語力も必要になるこの分野。
新高1生がつまづく最初の壁じゃないかと思います。
まあ、その前にも低い壁はいくつかありますけれど。
教科書第1章の計算分野は集団授業以外の時間にやっているので、集団授業では第2章からです。
各学年、先取りもしますが、復習もしなくてはいけません。
春期講習前半は先取りを、後半には復習をして茨城統一テストに備えたいと思います。