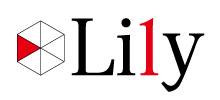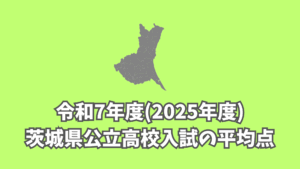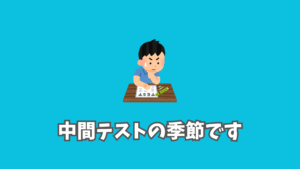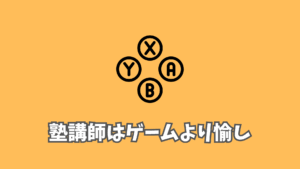どんなものにも良い面と悪い面があります。
とりわけYouTubeはそれがわかりやすいですね。
時間の浪費になってしまう人もいれば、最高の教科書として使う人もいます。
当たり前といえば当たり前ですが、上位層はYouTubeを武器として使います。
社会が得意なS君に聞いてみました。
「なんでそんなに覚えているの?普段どうやって勉強してる?」
「YouTubeを見てたら、覚えちゃいます」
その気持ち、よくわかります。
私も最初は特に興味がなかった戦国時代。
でも、面白いYouTubeを見ているうちに、戦国時代のことは結構覚えてしまいました。
こんなふうに、面白いものを何度も見ていると覚えてしまうものです。
五・一五事件は1932年というのも、1936年には二・二六事件が起こったというのも、頭に入ってしまって「年号が覚えられない」という状態になりません。
「なぜ覚えられる?」と聞かれても、勝手に覚えてしまったのですから答えようがないのです。
きっとS君もこんな感じだと思います。
今日、久しぶりにリリイ卒業生のYさんが塾に来ました。
現在高校2年生。春からついに受験生です。
ただ自習をしていただけですが、その様子を見ていたらYouTubeをうまく使っていました。
わからない単元をYouTubeで見ていたのです。
高校数学を教えている「及川先生」という方がいるのですが、神授業と言われる理由は見ればわかります。
とてもわかりやすいのです。
その及川先生の授業がYouTubeにアップされていて、それをYさんは見ていました。
同じ教科書を使っていても、勉強に使う人もいれば、人物写真に落書きして遊ぶ人もいます。
道具は使う人次第ってことですね。
「『ほら、学年1位の子だってYouTube見てるじゃん』と言ったって、それは勉強のためであって、あなたは完全に娯楽のためでしょう?」というやりとり、あちこちで繰り広げられてそうですね。
道具は上手に使いたいものです。