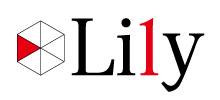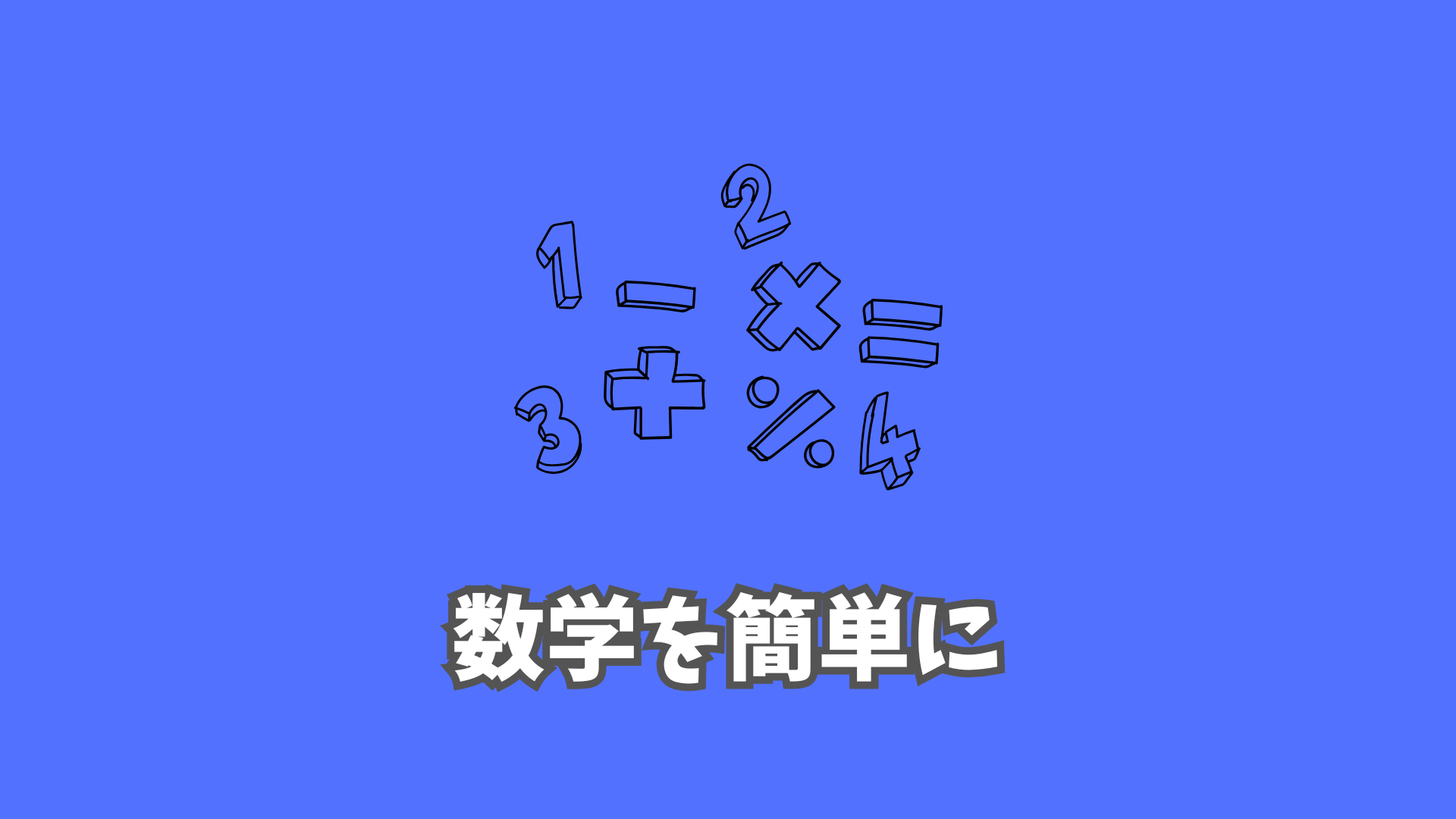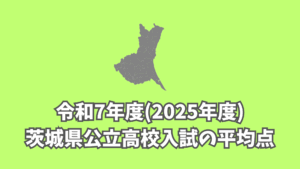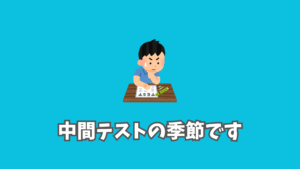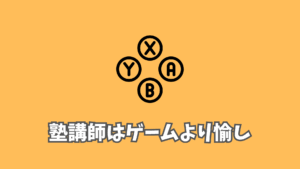「何のためにこんな勉強するんですか?」の筆頭に挙げられる平方根。
日常でルートなんて使ったことありませんよね。
まあ、日常で使う使わないの話になると、必要なのは小学校の算数までですね。
じゃあ、平方根とはなぜ学習するのか。
そもそも中学校の数学はなぜ学習するのか。
それはきっと、それ以上高度なことを学習するのに必要だからでしょう。
高度なことをやらないのであれば必要ありません。
それは英語や他の教科も同じこと。
必要がないと思う人にとっては必要ありません。
話は戻して平方根。
平方根に限らずですが、中学校で習う数学って「新しいルールを知って、実践する」という教科だと思います。
例えば「マイナスとマイナスを掛けたらプラスになるよ」という今までなかったルールを教えられて、それにのっとって問題を解いていきます。
こんなふうに、それぞれの単元の最初にルール説明があって、その後実践していくという流れです。
これってすでに小学生のころにもやっています。
「分数の割り算は、逆数にして掛ける」
こうやってルールを覚えて、何度もやったはずです。
勉強だけではありません。
例えば、道を歩いているとき「道の模様の線を踏んだら死ぬ」というルールを作って、友達や兄弟とそのルールを共有して遊んだりしましたよね。
それと同じようなものじゃないかなと思います。
平方根も「2乗すると5になる数を、5の平方根と言ってルート5って書くよ」というルール説明から始まります。
じゃあ、7の平方根は?
8の平方根は?
9の平方根は?
こうやってルールがしっかり理解されたかを確認しながら授業は進んでいきます。
やっていることは「この地面はマグマで、ここは通ったら死ぬから、ちょっと高いところを通らないと駄目ね」といった子どもの遊びと変わりません。
この「ルール説明」→「実践」というのは、日常生活ではいたるところに存在しています。
ゲームだって同じですよね。
こういうふうに考えると、数学も簡単にできるような気がしませんか?
高校数学になっても同じようなものです。
大事なのはまず最初にルールを理解すること。
そして、実践してみてルールを間違えて解釈していないか、ルールにのっとって正しく処理できているかを確認します。
それらをしっかりやっていれば数学なんて簡単簡単。
すぐに得意教科になりますよ。