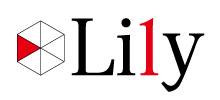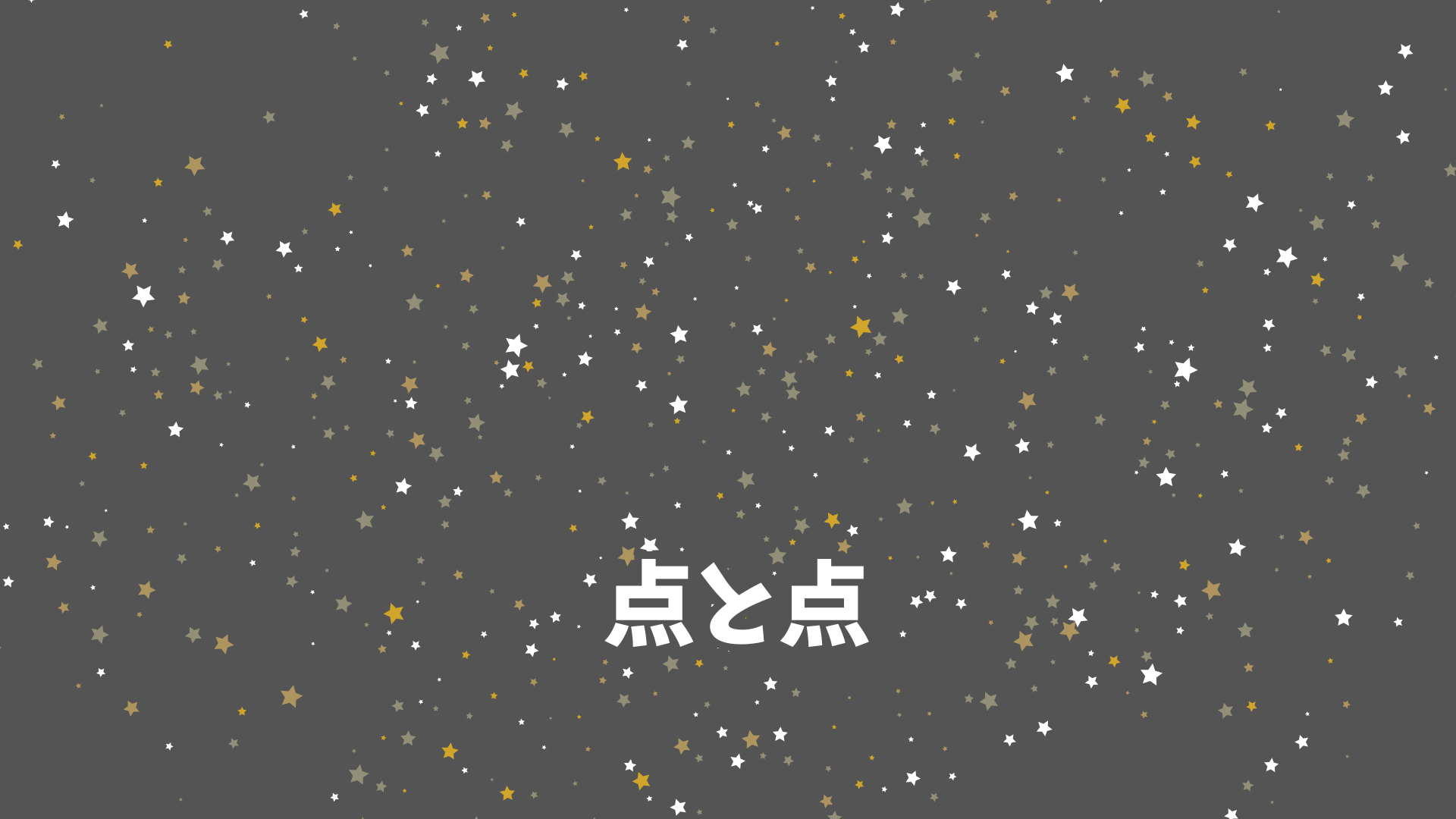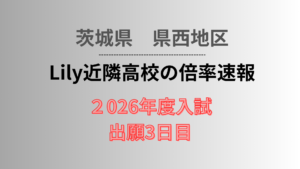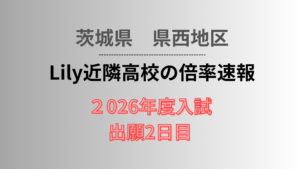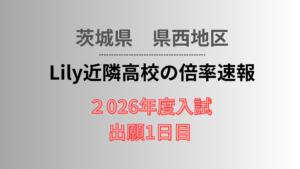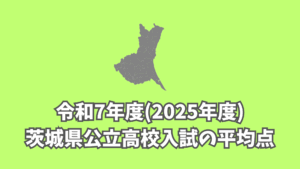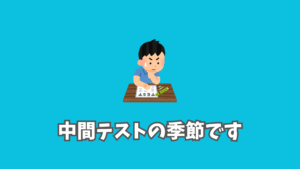歴史の授業は点と点を繋いで線にする作業だと思います。
豊臣秀吉が単位を統一して全国に行った、土地の面積の良し悪しや収穫高を調べた政策をなんというか。
 友人Y
友人Y太閤検地
1588年に豊臣秀吉が出した、農民から武器をとりあげる政策をなんというか。



刀狩令
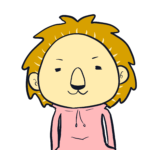
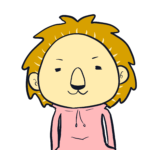
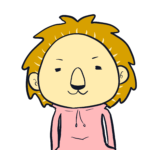
どちらも正解
この2つを別々の問題として捉えていてはいけません。
ある思惑で一本に繋がっているのです。
それは「米の生産力の向上」です。
生産力を向上させるには、まず現時点でどれくらいの生産能力があるかを確認しないといけません。
さらには、尺度が統一されていないといけませんね。
500ゼニーから1200ベリーになった、なんて言われても、単位が違っていたらそれが増えたのか減ったのかわかりません。
なので、まずは統一した基準を作らなくてはいけません。
さらに、比較するためには現時点の状況を記録しなければなりません。
それが太閤検地。
ちなみに太閤は秀吉のことです。
秀吉がやった検地なので太閤検地。
そして生産性を上げるために、農民からは武器をとりあげました。
それまでは農民も戦に駆り出されていたのです。
でもそれでは農民も米作りばかりしていられません。
戦でやられてしまっては、農耕もできなくなってしまいますしね。
ということで、農民は農業に専念させる。
そのための刀狩りです。
まあ、別に刀を取り上げなくても戦のときに農民を駆り出さなければいいんじゃない?と思うでしょう。
そりゃそうです。
でも、あえて刀狩りをしたのは「武器を持ってないから戦に来なくていいよ」という優しさではなく「一揆をさせないため」でしょう。
為政者がやる政策には、そんな表と裏があるものです。
そうやって生産能力を上げるのが目的で、これがわかっていると「太閤検地」も「刀狩」も一本に繋がります。
ではなぜ生産能力を上げたいのでしょうか。
この辺は考えればわかりますね。
生産能力が上がれば、豊かになります。
豊かになれば現体制を批判するようなことは起きません。
権力者は権力を持ったままでいられます。
また生産力の向上はそのまま国力の向上とも言えます。
他国から国を守るにはそういった力が必要なのです。
ということで、自分が日本を統一した豊臣秀吉の立場に立ってみれば、そりゃ「太閤検地」と「刀狩」をするよな~と思うでしょう。
こんなふうに、歴史上の人物になって考えてみると、それぞれがしたことも理解しやすくなると思います。
第一次世界大戦
ロシア革命
シベリア出兵
米騒動
原敬
も一本に繋がります。
他にも、1925年の普通選挙法と治安維持法も一本に繋がります。
まあ、言ってしまえば、歴史の線はほぼすべて繋がるわけですけれども。
そういう線のつながりを考えずに一問一答で覚えていると「古い順に並べよ」といった問題でできなくなってしまいます。
そこで繋げる作業の出番です。
それが授業。
ということで、社会の一番の勉強法は「先生の話をよく聞く」ということに尽きます。
教科書に書いていない部分をしゃべって点と点をつないでくれるのですから。
他の教科以上に授業が大事だと思います。
ということで、学校の先生の話もよく聞いて…と言いたいところですが……
「もう歴史、終わっちゃった」
ですよね……。
まあ、これを読んでいる7,8年生に向けてということで。
また9年生は高校生になったときに日本史や世界史を習うと思うのでそのときに活かしてくれればと思います。